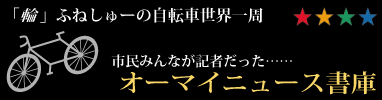
|
|
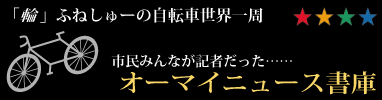
|
|
編集部の対応が全ての鍵を握っている(再) 私が前回書いた「なぜ市民記者は辞めてしまうのか」という記事が、大きな反響を呼んだ。編集部側の反論記事だけでなく、他の編集委員の方や市民記者の方からも相次いで関連記事が寄せられ、なおかつ外部のインターネットメディアにも波及して記事が掲載されていた。 一連の議論の中で、「なぜ市民記者は辞めてしまうのか」という見出しばかりが注目されて一人歩きしていた感があるが、私の思いの半分は、副題とした「編集部の対応が全ての鍵を握っている」に込めたつもりであった。「なぜ市民記者は辞めてしまうのか」を問いかけとするならば、「編集部の対応が全ての鍵を握っている」が、私なりの答案であった。 以下、「編集部の対応」に焦点を絞って書く。藤倉記者の「なぜ市民記者は辞めてしまうのかへの異論」、および平野編集次長の「そんなに単純ですか?市民記者が辞める理由って」。この2つの記事こそが、皮肉にも格好の題材である。 まず、この2つの記事が掲載された後、コメント欄には多くの書き込みがあった。その大半が批判意見であった。一部、藤倉記者や平野次長の主張内容を評価する声があったものの、それ以上に対応姿勢を批判する意見が目立っていた。記事の中身については賛否あったが、その文体や態度に対する反発が非常に大きかったということだ。 具体的に言えば、私が指摘した「市民記者の稼働率が3%」というデータ分析に対し、「3%は決して少なくない」という反論があった。「トップ記事の44%が編集部発」という指摘に対しても、編集部発の記事がいかに必要かという点についてあれこれ理由が述べられていた。論理的な是非はさておき、同じデータから異なる見解が導き出されたということ自体は、非常に面白いと思えた。 極めて残念だったのは、その書き方である。 象徴的には「大編集委員」という記述が挙げられる。掲載から半日も経たないうちに謝罪を添えて訂正する羽目になったことは、編集部として明らかにぶざまな失点であった。また、平野次長の会話の中に出てきた「編集を拒絶されました」という事実と異なる発言など、どうしてそんな余計なことを書いてしまうのだろうと、憤りを通り越して苦笑してしまう箇所がいくつもあった。 藤倉記者は面白いだろうと思って書き、編集部も面白いだろうと思って載せたのかもしれないが、そういった余計な表現の羅列が、記事全体の質を落としてしまっていた。余計なことを書くから、そのあと取り繕うのに、また余計な労力を費やしてしまうのだ。 繰り返すが、編集部側の意見に賛同するコメントもあった。私の記事に賛成ではないという意見も、当然あった。その点を踏まえて容易に類推できることは、編集部が、もっと丁寧な文体できちんと反論記事を書けていれば、コメント欄で袋叩きにあうこともなく、むしろ高い読者評価を得ることができたかもしれないということだ。実にもったいない。 答えるべき箇所はきちんと答え、認めるべき箇所は認め、ふざけた表現をせず、謙虚かつ真摯に「対応」してくれていれば、なにより編集部にとって大いにプラスであったはずなのだ。 重ね重ね残念な結果であったと、言わざるを得ない。 私は編集業界については素人である。だから、取材の仕方であるとか、文章を校正するにあたってのしきたりなどは、ほとんど知らない。業界の方々から見たら、「分かってないなあ」と思える面が多々あるかもしれない。しかし、おそらくそれは、大半の市民記者の方々が同じだろう。 一方で私は、大学卒業以来、主にサービス業に従事し、営業職として、多くの人々の要望や、ときに苦情と相対してきたという経験がある。その分野に詳しい知識を持った玄人だけを相手にするのではなく、むしろ何も知らない素人のお客様を大事にし、懇切丁寧に応対するという術を学んできたつもりである。 その目線から見ると、創刊以来1年余り、オーマイニュース編集部の、市民記者や読者に対する対応は、「ど下手」の一言に尽きる。(念のため、全てがそうであるとは言わない。至極まっとうな対応をしていただけることも多いが、それは当たり前のことであり、わざわざ褒めるに値しない) この点を真剣に改善しない限り、市民記者の登録数も実働率も、サイト全体の閲覧数も上がることはなく、編集部はその現状を直視し咀嚼することすらできないだろう。あるいは、業界慣習に慣れたプロ記者ばかりの閉じたニュースサイトとして、創刊宣言の理想は完全に堕ちてしまうであろう。不特定多数の素人市民記者の記事ばかり扱うよりも、編集部好みのテーマでしっかり記事を書いてくれるプロ記者を相手にしたほうが、はるかに苦労がなく楽であることは、容易に窺い知れる。 それでもよいなら、それでいいし、さっさと「市民みんなが記者だ」の創刊宣言を廃してくれたらいい。そのほうがずっと分かりやすい。創刊宣言に謳われている「ニュースの仕組みを変える」も「最小限の編集、最大限の事実確認」も「謙虚に学びながら挑戦」も、現在のオーマイニュースの実情を見ると、あまりに空々しい。 「プロ記者がオーマイニュースを語りますよ」 「編集部のPOV」 藤倉記者と平野次長、それぞれの反論記事の副題であるが、これだけ切り取ってみても、いかに創刊宣言の理想から、かけ離れてしまっているかが分かる。(POVはpoint of viewの略で「視点」という意味であるらしいが、こういった用語遣い自体が、中学生からお年寄りまでが参加している市民記者メディアにおいて、明らかにズレている) 最後に、ずいぶん前のことになるが、平野次長が元旦に書かれた記事「【極私的2006年回顧】言われたら、言い返そうぜ Web2.0」のコメント欄からの引用をもって、私の編集委員としての職務を終わりとしたい。 #97(平野次長) 「私としては自分が経験したことのある労使交渉のアプローチ(バラバラに意見を言っている労組側が一本にまとまるならば、経営側もそこまで歩み寄って妥結、というアプローチ)の連想で臨みました」 #119(木舟) 「市民記者および旧オピニオン会員に対する編集部の立ち位置として、労使という関係で捉えていらっしゃるとしたら、いささか疑問に感じます。私の個人的見解としては、市民記者、旧オピニオン会員含め、全てのオーマイニュース読者は、決してオーマイニュースに雇用されているわけではありません。労組という括りで考えていらっしゃるとしたら、少し違うのではないかと思います。むしろ、顧客(お客様)として捉える視点が、欠けているのではないでしょうか? (中略) しかし、それはオーマイニュースに限らず、不特定多数の顧客(お客様)を相手にする一般企業であれば、ごく当たり前のことです。むしろそういった苦情や意見や指摘の類を、いかに消化し、改善をしていくか、その点に、より多くの顧客(記者および読者)を得られるかどうかがかかっているのではないでしょうか? (中略) しかし、市民記者含め、オーマイニュースの全ての利用者に対して、より慎重かつ謙虚な姿勢(決して卑屈になるわけではなく)で対応していただくことを望みます。そのほうが、より良い結果が得られるのではないかと思います」 私が言いたいことは、このときとほとんど変わっていない。その事実に愕然とする。 結局この1年、オーマイニュースは「市民メディアとしての成功」の手掛かりすら得られないまま、ずっと同じところを彷徨っているように見える。 おしまい。 (市民記者編集委員 2007年9月─11月) 【編集部注】 木舟記者が引用している平野のコメントについて、引用部分だけでは文脈不在の断片情報で意味がわかりにくいので、平野本人に確認しました。(以下、平野記) これは旧オピニオン会員を市民記者会員に一本化した(2006年11月)際の交渉スタイルについて説明したコメントの一部です。「旧オピニオン会員の多種多様な意見」対「編集部」の関係を、「N対1の関係」としてとらえ(Nとは多数の意味)、その「N対1の交渉ごと」の比喩として、私自身の交渉経験にもとづき、「労使交渉のアプローチ」と表現いたしました。木舟記者は引用しておりませんが、私のコメントには、以下の文章が続き、その部分が「N対1の交渉スタイル」の説明のエッセンスです。 自分の主張を勝ち取りたいなら、労組はだれかが旗を振って、意見を一本にまとめなくてはならない。だから百家争鳴のオピニオン会員も自分たちの意見で通したいなら、どなたかが旗を振って、意見を一本にまとめてください、もしまとまるならば、運営サイドもその線にいたしましょう、と。そこでオピニオン会員のなかでも、当方に最後まで残った2案のひとつに近い意見を開陳された△△さんに、「その線で (Nであるオピニオン会員のみなさんがひとつに) まとまるならば、こちらも歩みよる用意がありますよ」と申し上げた次第です。 〔△△の部分はハンドルネームをマスクしました。丸カッコ内は意味を補うため2007年11月2日時点での加筆です〕 したがって、「N対1の交渉スタイル」の比喩として使っている「労使」「労組」という単語をとらまえて、編集部は自分たちを「使用者」、市民記者・旧オピニオン会員を「労働者」「被雇用者」と考えている、けしからん、などと解釈していただきますと、それはまったくの誤解です。とはいえ、不特定多数からの苦情や意見や指摘の類を上手に消化し、改善につなげなければならない点については、木舟記者のご指摘の通りであると今今現在でも反省し、その方向で努力しております。誤解を招くコメントをエントリーしました点、どうぞお許しください。 (2007年11月3日掲載)
|